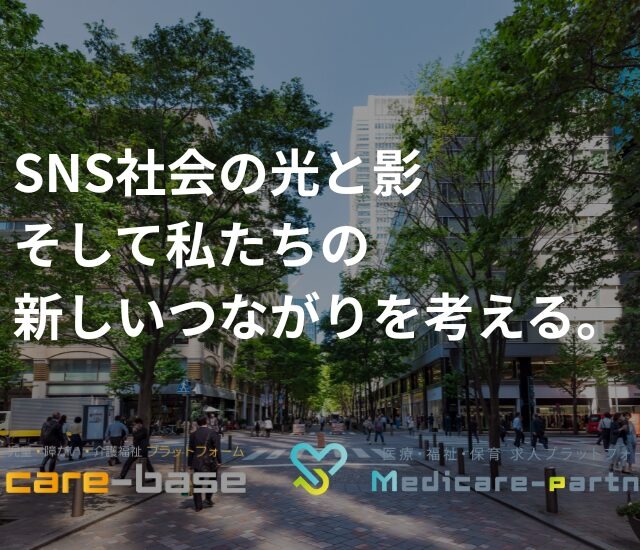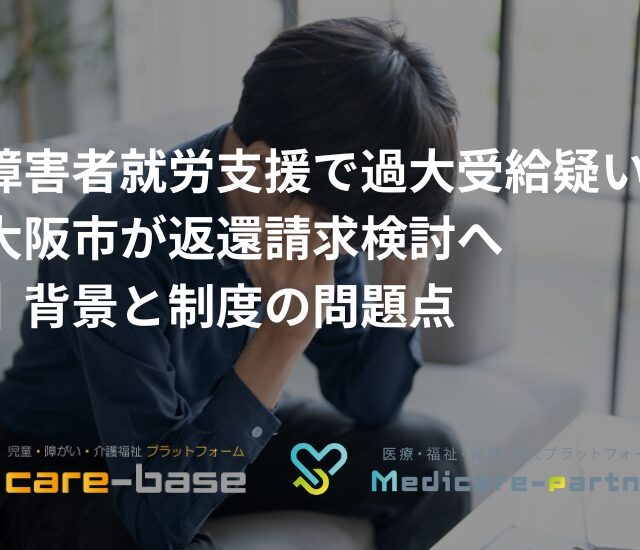1. 障害福祉報酬や介護報酬への物価スライド制導入の要望
2025年1月、参議院議員有志が厚生労働大臣に対し、障害福祉報酬や介護報酬に物価や賃金の上昇に応じたスライド制の導入を要望しました。これは、食材料費の高騰や人材流出が事業継続に深刻な影響を与えている現状を受けたもので、報酬が公定価格で決められているため、民間企業のような柔軟な賃上げが難しい点を指摘し、期中改定の検討も求められています 。
2. 社会保障改革に向けた3党合意と協議体の設置
2025年2月、自民党、公明党、日本維新の会の3党首が、教育無償化と社会保障改革を柱とした合意文書に署名しました。この合意に基づき、現役世代の保険料負担軽減を検討する協議体が設置され、2026年度から順次実行される予定です。協議体では、応能負担の徹底や医療・介護産業の成長産業化などが検討されます 。
3. 地域包括ケアシステムの構築と医療・介護人材の確保
政府は、2025年問題に対応するため、地域包括ケアシステムの構築を進めています。これは、高齢者が住み慣れた地域や自宅で可能な限り長く自分らしい暮らしを継続するための支援やサービスを提供する体制で、地域全体で連携した医療・介護サービスの提供や在宅医療・介護の推進が含まれます。また、医療・介護人材の確保に向けて、処遇改善や資格取得支援、外国人材の受け入れなども進められています 。
これらの制度的な取り組みは、福祉業界が直面する課題に対して前向きに対応し、より良いサービス提供と職場環境の実現を目指す動きとして注目されています。
4. 介護職員の賃上げと保険料抑制の両立
政府は、介護職員の賃上げを実行しつつ、保険料の上昇を抑制する方針を打ち出しました。デジタル技術やリスキリング(学び直し)を活用して労働生産性を向上させ、給付増を抑えることで、持続可能な医療・介護制度の構築を目指しています 。
5. 介護保険制度に新たな「複合型サービス」を導入
2024年度の介護保険制度改正では、訪問介護と通所介護を組み合わせた新しい「複合型サービス」の創設が検討されています。これは、地域包括ケアシステムの深化と、介護人材不足への対応を目的としています 。
6. 社会保険の適用拡大
2024年10月から、従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトも社会保険の適用対象となります。これにより、非正規労働者の社会保障が強化され、働き方の多様化に対応する制度改革が進められています 。
7. 育児・介護休業制度の拡充
2025年4月から、育児休業や介護休業の対象者範囲が拡大され、残業免除の対象となる労働者の範囲も広がります。これにより、仕事と家庭の両立がしやすい環境が整備され、ワークライフバランスの向上が期待されています 。
8. 介護保険料の所得再分配機能の強化
介護保険制度では、被保険者間の所得再分配機能を強化するため、高所得者の保険料負担を引き上げ、低所得者の負担を軽減する見直しが行われます。これにより、介護サービスの持続可能性と公平性が高まります 。
9. 高年齢雇用継続給付の見直し
2025年4月から、高年齢雇用継続給付の給付率が最大15%から10%に引き下げられます。これにより、企業は給付金に頼らず、高年齢労働者が働き続けられる職場環境の整備が求められます 。
10. 障害者雇用制度の見直し
2025年4月から、障害者雇用促進法の施行規則が改正され、除外率設定業種の除外率引き下げや、障害者の雇用状況報告義務の対象事業主の範囲が見直されます。これにより、障害者の雇用促進が進められます 。
11. 高等教育費の負担軽減
大学などの高等教育費の負担軽減のため、奨学金の範囲拡大や授業料後払い制度の導入が検討されています。これにより、教育の機会均等が促進され、若者の学びの支援が強化されます 。
12. 住宅セーフティネットの拡充
住宅確保要配慮者に対する住宅の提供や家賃補助、住宅債務保証の拡充が進められています。また、改正住宅セーフティネット法の見直しを早急に行い、必要な法改正や予算拡充が求められています 。
13. 出産費用の保険適用の検討
これまで保険が適用されなかった出産費用について、2026年を目途に保険適用の導入が検討されています。これにより、出産に伴う経済的負担の軽減が期待されています 。
これらの制度改革は、福祉業界における持続可能性の確保や、国民の生活の質の向上を目指すものであり、今後の社会において重要な役割を果たすことが期待されています。