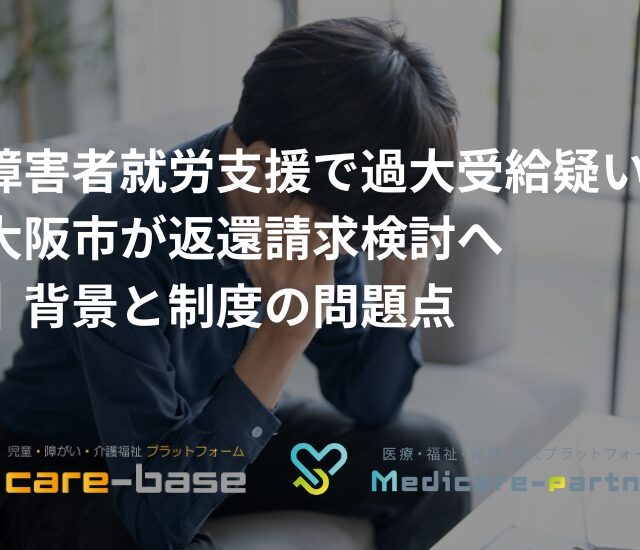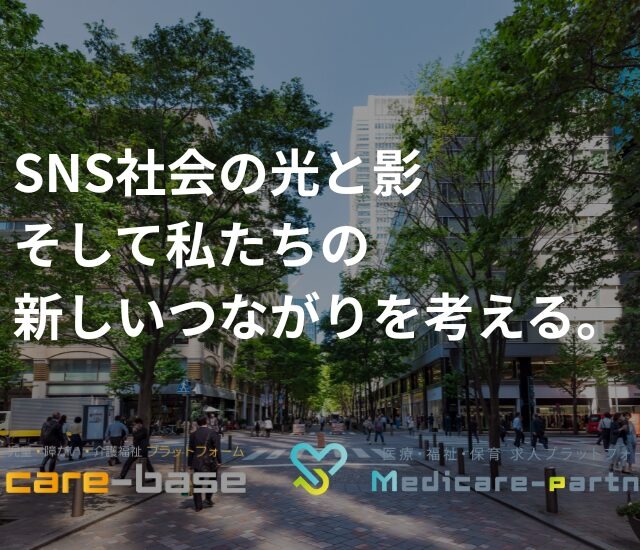本評価制度は、就労移行支援事業所において働く職員一人ひとりが、専門性を高めながら利用者支援の質の向上を目指し、安心して業務に取り組める職場環境を築くことを目的としています。
就労移行支援は、障がいやさまざまな課題を抱える方々の「働きたい」という思いを実現するために、日々の支援の積み重ねが何よりも重要です。その中で、職員が自身の役割や強みを理解し、成長実感を持ちながら働き続けられることは、支援の質と継続性の確保に不可欠です。
本制度では、個々の職員の業務遂行状況を「利用者支援」「チーム連携」「事務処理」「自己研鑽」「外部対応」「組織貢献」の6つの視点から評価し、公平・透明な運用を行います。評価は単なる結果の測定ではなく、行動やプロセスの振り返りを通じた対話と成長の機会と位置づけています。
また、この制度は評価者と被評価者の信頼関係に基づき、双方向のフィードバックを大切にします。評価結果は、今後の人材育成・配置・研修機会の提供に活用し、職員一人ひとりのキャリア形成と、組織全体のサービス品質向上を目指していきます。
制度の運用にあたっては、評価項目の明確化と評価の透明性を重視し、定期的な見直しを行いながら、より良い評価制度として発展させてまいります。
1.利用者支援
利用者一人ひとりに対する支援の質、成果、継続性を総合的に評価します。
●個別支援計画に基づいた支援の実施状況
支援計画を理解し、本人のニーズに沿った対応がされているか。計画に沿った目標・手段をきちんと現場で反映できているか。
●利用者との信頼関係の構築度
話しかけやすさ、丁寧な傾聴、相手の立場に立った支援ができているか。利用者からの相談件数や満足度も参考に。
●就職実績および職場定着支援の成果
就職支援が計画的に行われ、実績や定着率が高いか。また、定着支援が利用者や企業にとって有益だったか。
●支援記録の正確性と適時性
記録が簡潔かつ客観的にまとめられているか。期日までに入力され、記録に齟齬がないか。
●支援プログラムの質と実施頻度
グループワークや講座(就職準備、コミュニケーション等)の内容が利用者に合っており、継続して実施できているか。
●利用者の目標達成に向けた進捗管理能力
進捗状況を把握し、目標達成に向けた助言や方針転換を適切に行っているか。
●面談やアセスメントの実施内容の充実度
定期的に面談を行い、アセスメントを通じて利用者の状態や課題を的確に把握しているか。
2.チーム連携・協調性
他職種との情報共有、信頼関係、円滑な連携体制を構築できているかを評価します。
●他職種との情報共有の頻度と質
支援会議や日報、引継ぎなどで他スタッフと必要な情報を適切に共有しているか。
●会議・ケース検討会での積極的な発言
意見や提案を積極的に出し、より良い支援に貢献しているか。
●同僚への支援・フォロー体制の構築力
業務が集中している職員や新人を支える姿勢があるか。
●トラブル発生時の冷静かつ迅速な対応力
チームとしての連携を崩さず、適切に対応できているか。
●役割理解と責任遂行の一貫性
自身の職務範囲を理解し、求められる役割を的確に実行できているか。
●チーム目標に対する主体的な関与
就職率向上や定着支援強化などの組織目標に対して、具体的な行動を起こしているか。
●課題やミスへの改善提案の姿勢
チームで発生した課題に対して、前向きな解決策を考えているか。
3.事務処理・報告業務
正確でタイムリーな記録業務、報告、書類作成能力を評価します。
●帳票や記録の正確性と納期遵守
モニタリング記録、ケース記録、利用実績の記録などが適切かつ期限内に完了しているか。
●国保連請求に関する業務理解
基本的な請求業務の流れや加算の考え方を理解しているか。補助業務にも対応できているか。
●電子記録システムの操作と活用度
日常業務でのPC・クラウド操作に不安がなく、システム入力が正確に行われているか。
●書類作成能力(報告書・依頼文など)
文章の構成・敬語・表現が適切で、読み手に誤解を与えない内容になっているか。
●文書管理と守秘義務の徹底
個人情報の取り扱いやファイル保管に対して高い意識を持っているか。
●監査・実地指導対応の書類準備力
適切な保管、フォーマット遵守、監査対応の理解があるか。
●報告・連絡・相談の質とタイミング
状況に応じた迅速なホウレンソウができており、上司・関係者との意思疎通が円滑か。
4.自己研鑽・スキルアップ
自身のスキル向上への意識と、実際の学習・実践度を評価します。
●障がい福祉・法制度に関する知識更新
障がい特性、障がい者雇用、報酬改定などの新情報を自ら調べて理解しているか。
●外部研修・eラーニング等の受講率
自主的に学びの機会を活用しているか。研修参加後の実践報告ができているか。
●資格取得への取り組み姿勢
ジョブコーチ、福祉専門職資格の取得や、更新手続きに前向きに取り組んでいるか。
●支援スキル(面接同行、職場開拓等)の習得度
現場で必要な実践スキルを自ら磨き、活かしているか。
目標設定と振り返りの明確さ → 年間・月間目標を設定し、業務改善や成長につなげているか。
学びを現場に反映させた実践力 → 研修で得た知識を現場で共有・実践しているか。
職員間での知識共有・勉強会開催 → チーム内での学びの循環に貢献しているか。
5.利用者・企業との外部対応
対外的な対応力、連携・折衝のスキルを評価します。
●企業開拓や職場見学の提案・実施実績
新規企業の開拓を行っているか、実習の受け入れ交渉ができているか。
●利用者の職場マッチング精度
利用者の特性と企業ニーズを的確に見極め、適切な就職先を提案できているか。
●就職先との連絡・報告体制の整備度
定着支援として定期的に就職先と連絡を取り、情報共有が行われているか。
●面接同行・企業訪問時の対応マナー
対企業に対して信頼感のある接し方・説明ができているか。
●企業ニーズに応じた提案力
採用側の課題を把握し、企業にとって有益な支援内容を提示できているか。
●企業とのトラブル調整や対応力
利用者と企業間で問題が生じた際、誠実かつ冷静に対応しているか。
●地域資源とのネットワーク活用力
ハローワークや他福祉機関と良好な関係を築き、支援に生かしているか。
6.組織貢献・改善提案
組織の改善・活性化に向けた行動、主体性、周囲への影響力を評価します。
●マニュアル改善や業務効率化提案の実施
現場で使える手順書の改善提案や、非効率業務の見直しに貢献しているか。
●サービス向上への建設的提案
利用者満足や成果向上に向けて、新しいアイデアを出しているか。
●内部研修や勉強会の企画・実施経験
所内研修を立案・実施し、職員間のスキルアップに貢献しているか。
●後輩・新人職員の育成支援
OJTや日常業務で積極的に指導・支援しているか。
●報酬改定・制度変更に対応する姿勢
制度変更に前向きに対応し、柔軟に業務を調整できているか。
アンケート・満足度調査をもとにした改善行動
利用者・企業の声を反映し、具体的なアクションに落とし込んでいるか。
目標達成に向けた自発的行動・姿勢
自分の役割を超えてチームの成果に貢献しているか。
― 情報の壁を越え、支援のチームをつなぐ次世代福祉プラットフォーム ―
近年、障がい福祉や高齢福祉の現場では、支援の質を高めるための「地域連携」の必要性がますます高まっています。しかし現場では、情報の分断・支援者間の連携不足・属人的な支援計画の運用といった課題が顕在化しています。
そうした中、福祉・医療・介護・教育など多分野の関係機関をシームレスにつなぐ革新的なプラットフォームが「care-base(ケアベース)」です。
■ 実際の地域連携モデル:care-base導入事業所の例
たとえばA市のある就労移行支援事業所では、care-baseを導入後、施設内作業→施設外就労→障がい者雇用→定着支援までを一気通貫で管理可能に。
その結果、「支援の抜け漏れが減った」「関係機関同士の信頼関係が構築された」「多職種間の会議時間が短縮された」といった効果が現れています。
■ care-baseで目指す“地域まるごと支援”の未来
care-baseを活用することで、支援機関同士が組織や立場の枠を超えて「一人の利用者」のためにつながる仕組みが整います。
地域全体がチームとして動く「地域まるごと支援」の実現は、今後ますます求められる福祉のスタンダードです。
情報をつなぎ、支援をつなぎ、地域をつなぐ――。
care-baseは、そんな福祉の未来をともにつくるプラットフォームです。