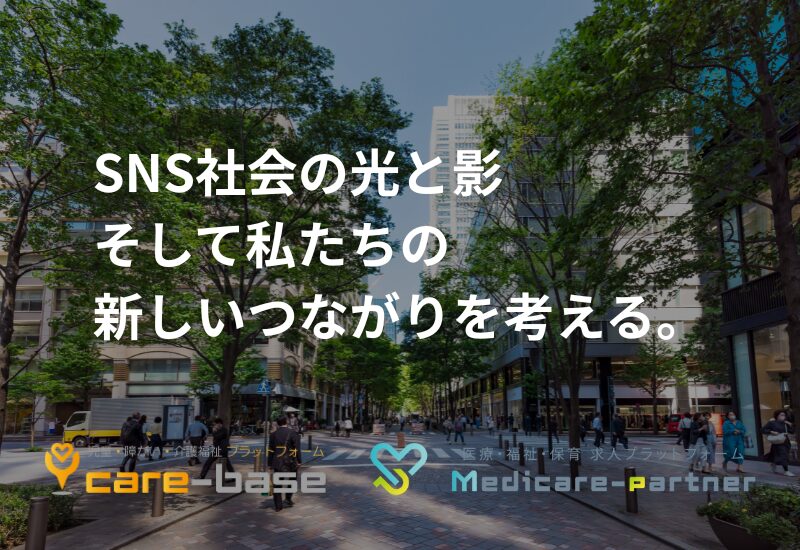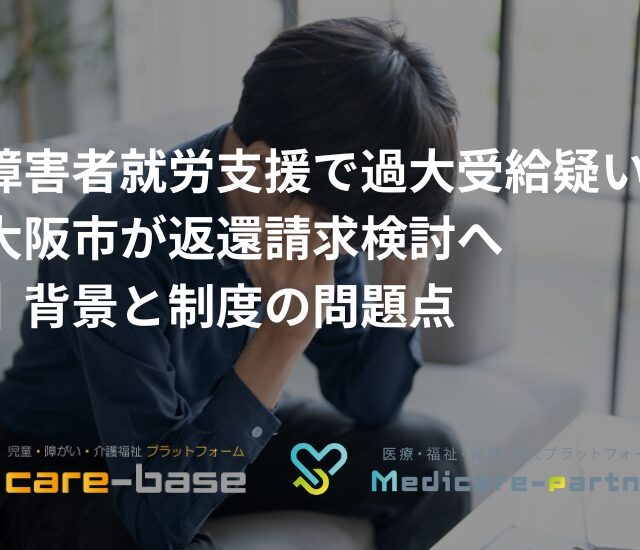第1章 かつてSNSは「世界をつなぐ希望」だった
2000年代後半から広がったSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、人と人を結び、世界を変える力を持っていました。
Facebookが「世界中の人をつなぐ」ことを掲げ、Twitter(現X)が誰もが発信者になれる時代を切り開き、Instagramが日常をアートに変え、LINEが家族・友人との日常的な連絡手段になった。
SNSは、距離も時間も越えて「人を近づける」奇跡のツールでした。
しかし2020年代後半に入り、SNSの空気は変わりつつあります。
「もう疲れた」「怖い」「やめたい」そう語る人が増えています。
今、静かに進行しているのが、SNS離れです。
そしてその背景には、アカウント乗っ取りという「信頼の崩壊現象」が深く関わっています。
第2章
増え続けるアカウント乗っ取り―デジタル社会の新たな脅威―
● SNSアカウント乗っ取りの実態
SNSアカウントの乗っ取り被害は、ここ数年で爆発的に増加しています。
警察庁や情報処理推進機構(IPA)の調査によると、2024年にはSNS関連の不正ログイン報告件数が前年比約30%増加。
特にInstagramやLINEでの被害が顕著です。
「突然ログアウトされ、再ログインできなくなった」
「友人から“あなたのアカウントが怪しい”と連絡が来た」
「知らないうちに詐欺DMを送っていた」
こうした被害報告が日常的にSNS上を飛び交っています。
● 乗っ取りの主な手口
アカウント乗っ取りは巧妙化しています。代表的な4つの手法を見てみましょう。
1. フィッシング詐欺
偽のログイン画面をメールやDMで送付し、本人がID・パスワードを入力するよう誘導する。
InstagramやLINEを装う偽サイトが多く、見た目も本物そっくりです。
2. マルウェア感染型
悪質なアプリ・リンクを踏むと端末にマルウェアが侵入。
保存されたSNSログイン情報が抜き取られます。
3. パスワードリスト攻撃
他サービスから流出したID・パスワードを使って、SNSに総当たりでログインを試す。
同じパスワードを使い回している人が狙われやすい典型です。
4. 第三者アプリ連携型
「フォロワーを増やす」「投稿を分析する」などの外部アプリにSNS連携を許可すると、裏でデータが抜かれるケースもあります。
第3章
乗っ取られた後に起こる“信用の崩壊”
―アカウントを奪われると、被害は想像以上に広がる―
・詐欺メッセージがフォロワー全員に送られる
・プロフィールや投稿が改ざんされる
企業・団体アカウントなら信用失墜、炎上、顧客離れへ
たった一度の乗っ取りで、「築いてきた信頼」が一瞬で消えます。
特に個人事業主や福祉・教育関連の施設では、SNSが“情報発信の生命線”であることも多く、乗っ取りは経営リスクそのものです。
第4章 なぜ今、人々はSNSから離れ始めているのか
一方で、近年は「SNSをやめる人」も増えています。これは偶然ではなく、構造的な変化です。
● SNS離れを示すデータ
総務省の「通信利用動向調査」(2024年)によると、20〜30代のうち「SNSを以前より使わなくなった」と回答した人は全体の約32%。また「投稿をしない・見るだけ」に移行した“サイレントユーザー”も増加しています。
● SNS離れの5つの理由
1. 情報過多による疲労
ニュース、広告、個人投稿、動画…情報が途切れない。常に他人の生活を見せつけられることで、脳が休まらない。
2. 承認欲求と比較のストレス
「いいね」が自己評価の基準になり、他人と比較して落ち込む“SNSうつ”が社会問題化しています。
3. プライバシーと安全の不安
・投稿の拡散
・スクリーンショット
・なりすまし
「誰が見ているか分からない」ことが心理的負担に。
4. 誹謗中傷と炎上の恐怖
発言が切り取られ、攻撃されるリスクが常につきまとう。特に社会的立場のある人ほど慎重になり、発信を控える傾向。
5. リアルとの乖離
SNSでは「理想の自分」を演じがちで、現実とのギャップに苦しむ人が増えています。
こうした要因が積み重なり、人々は**「つながることの疲れ」**を感じ始めています。
第5章 SNSは“便利さ”の代償として信頼を失った
SNSは元々、「誰もが自由に発信できる民主的な空間」でした。しかし、広告モデル・アルゴリズム・拡散文化が進むにつれ、その空間は次第に「刺激を競う場」へと変化していきました。
その結果、人々は安心よりも不安を感じるようになったのです。
「何を発信しても誰かに見られている」
「本音を書けば炎上する」
「友達の投稿に疲れる」
SNSが社会的インフラになった今、私たちは便利さと引き換えに**“心の平穏”**を失いつつあります。
第6章 SNS疲れからの脱出―デジタル・デトックスの広がり―
こうした中で、近年注目されているのがデジタル・デトックスです。
スマホやSNSから一時的に距離を置き、リアルな人間関係や趣味・自然との関わりを取り戻す動きが広がっています。
「夜9時以降はSNSを見ない」
「週末はアプリをアンインストールする」
「通知を切って1日を過ごす」
小さな工夫が、心のリズムを整え、ストレスを軽減します。
第7章 SNSをやめることは“逃げ”ではない
SNS離れは「社会からの孤立」ではなく、むしろ「情報に支配されない選択」としての成熟です。
SNSに価値がなくなったわけではありません。問題は、どう使うか・どの距離を取るかにあります。
例えば・・・
・二段階認証を設定する
・不審なDMを開かない
・公私のアカウントを分ける
・必要な情報だけをフォローする
これらの基本対策で、SNSはより安全で快適なツールに戻ります。
第8章 変わる「つながり」の形―安心と信頼を軸にしたデジタルへ―
SNS全盛期を経て、私たちはようやく「つながることの意味」を見直し始めています。
これから求められるのは、「誰とでもつながるSNS」ではなく、「信頼できる人と安心してつながる空間」です。
たとえば、教育・医療・福祉・介護といった領域では、個人情報や支援記録を扱うため、オープンSNSはリスクが高すぎます。
その代わりに、専門職同士や家族が限定的に情報共有できるセキュアなプラットフォームが注目されています。
第9章 信頼の再構築へ―care-baseが示す新しい方向―
SNSの疲弊と乗っ取り被害が拡大する中で、「安心してつながる」という視点から注目されているのが、児童・障がい・介護福祉プラットフォーム care-base(ケアベース) です。
care-baseは、SNSのように情報を共有できる一方で、セキュリティと守秘性を最優先に設計された“ケアのためのデジタル基盤”。
不特定多数ではなく、支援者・家族・関係機関のみが限定的に参加できるため、情報漏えいリスクが極めて低く、信頼をベースにした交流が可能です。
SNSの「開かれすぎた世界」から、care-baseのような「信頼でつながる世界」へのシフトは、これからのデジタル社会の象徴的な動きといえるでしょう。
●結論
SNSを超えて、“本当のつながり”を取り戻す時代へ
SNSは、私たちに無限のつながりを与えました。
しかし、同時にその“無限さ”が、人間の信頼と安心を侵食してきたのかもしれません。
SNS離れや乗っ取り被害は、「人は安全で、心地よいつながりを求めている」という自然な反応です。
これからのデジタル社会は、便利さよりも 信頼・安全を中心に再設計されるべき時代に入りました。
そして、その先駆けとして、―福祉・教育・介護分野で安心して情報を共有できる仕組み―
care-base のような専門プラットフォームが注目されているのです。
――――――――――――――――――――
care-base[ケアベース]児童・障がい・介護福祉プラットフォーム https://care-base.jp
――――――――――――――――――――
▶ユーザー登録 https://care-base.jp/register
ユーザー登録して事業所に気軽にチャットで問合せが可能!!
――――――――――――――――――――
▶事業所掲載申込み https://care-base.jp/office_application
無料掲載からネット検索・SEOが上位表示を実現!!
――――――――――――――――――――
▶Work on(作業依頼)アカウント作成 https://care-base.jp/company/register
企業からのお仕事受注を効率化して生産性向上と障がい者雇用に繋げよう!
――――――――――――――――――――
医療・福祉・保育求人プラットフォームMedicare-partner[メディケアパートナー]
――――――――――――――――――――
▶求人掲載はコチラ https://medicare-partner.jp/company/register
無料掲載からでき有料プランも安心の定額で求人掲載が可能!!
――――――――――――――――――――
▶求人ユーザー登録はコチラ https://medicare-partner.jp/register
ユーザー登録で履歴書・職務経歴書がWEB上で作成・ダウンロードができる!!
――――――――――――――――――――
▶学校・人材紹介会社・外国人雇用(監理団体・登録支援機関)登録 https://medicare-partner.jp/agent/register
――――――――――――――――――――